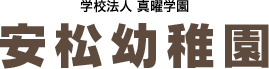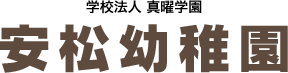理事長エッセイ
先生の熱意と指導力が安松幼稚園の誇り
- ホーム
- 理事長エッセイ
雑誌『致知』の取材を通して
幼稚園の責務は 日本の文化を次の世代に伝えることにある
―― 国語力により その国特有の美的感受性が養われ
文化 伝統 情緒 などが 次の世代に受け継がれていく ――
今年の3月末に、雑誌『致知』の編集者から「一度お会いして取材をしたい。そしてある方と対談してほしい」という依頼がありました。(『致知』は約10年前にも本園まで取材に来られ、その様子はHPにupしています)「東京までは行けません」と一旦はお断りしたのですが、大阪まで行くから是非にという強い要望があり、4月7日に新大阪のホテルでの取材・対談となりました。
その様子は、『致知6月号』に掲載されています。6月号のテーマは『読書立国』でありましたが、私は、読書に限定せずに、文化論から話を展開しました。ここにまとめてみましたので、お読みいただければ嬉しいです。
【Ⅰ】安松幼稚園設立の根本
今年度は安松幼稚園創立77周年にあたります。
安松幼稚園では、日本の文化を、次代を担う子供達に伝えることが学校の大きな責務の一つだと考えています。
昭和24年(1949年)の大阪府への安松幼稚園の設立認可申請書(初代代表:安井玄龍氏による)には、「心身共に健全なる幼児の育成に努め、以て文化日本の建設に九牛の一毛にてもお役に立つべく決心した次第です」と記されています。
当時の時代背景に思いを致す時、戦争に敗れた日本の復興は幼児教育から始まると考え、子供達に日本の文化を伝えることの重要さが記され、幼稚園設立に向けての熱い想いが伝わってきます。
【Ⅱ】一国の文化はその国の国語に集約される
藤原正彦先生には、「祖国とは国語」という著書があります。言語を損なわれた民族がいかに傷つくかは、世界には多くの例があります。その著書の中で「『祖国とは国語である』のは、国語の中に祖国を祖国たらしめる文化、伝統、情緒などの大部分が包含されているからである。祖国が血でも国土でもないとしたら、これ以外に祖国の最終的アイデンティティーとなるものがない」と記されています。私も小さい頃に読んだドーデの著書「最後の授業」の中にある、戦争に敗れ占領された地域のある小学校での最後の授業で、先生が児たちに「国は占領されても、私達が〇〇語(母国語)を忘れない限り国は滅びない」と板書し叫んだ最後の場面、何十年もたった今でもその感動は私の胸に残り、思い返せば涙が溢れます。ドーデも『祖国とは国語だ』と叫んだのです。
【Ⅲ】国語教育の充実こそ国の基盤
安松幼稚園では、日本の文化を次の世代に伝えたい。その為には、日本人の持つ情緒をどのようにすれば子供たちに伝えることができるかという観点から、次の領域・単元をカリキュラムに取り入れています。
・四文字熟語 ・ことわざ ・俳句 ・和歌 ・論語 ・吉田松陰先生などが残された文
・古典の朗誦(平家物語、枕草子、徒然草、方丈記など) ・近代古典 など
選定の基準は、子供の身の回りで起きること、生活体験からスッと理解しやすいもの。 なおかつ 今後の人生において身につけてほしい感性・情緒・知識が含まれているか
などで、学年により教材は変わっていきます。年長児では、当園作成の『こころの詩』という教科書を用いています。
安松幼稚園では、例えば歌唱指導においても、国語教育の観点をも考慮しながら選曲しています。
それは幼児期にこそ、子供達に綺麗な日本語に触れさせたいという思いからです。その際、幼稚園における有効な教材の一つとして思いつくのは、綺麗な日本語で書かれた詩からなる唱歌・童謡です。唱歌・童謡を通じて、子供達は、北原白秋 西條八十 野口雨情などの格調高い日本語の詩に、歌う楽しみを通じながら触れることができる。これがまさに唱歌・童謡です。さらには日本の情緒を伝える日本音階を用いた曲や民謡なども取り入れています。(もちろん歌う楽しさや音楽そのものの本質を伝えるのは当然です)
【Ⅳ】型の伝承
既に述べましたように、私は『一国の文化はその国の国語に帰着する』と考え、もっと言うと、『日本の文化の源は古典(和文・漢文などの書き下し文)である』と思っています。古典は集積された人間の知恵であり、それを学ぶことが『型の伝承』になります。
いまどき型なんて言うと、個性や自由が失われると反論する人が多くいます。すなわち『型』と『個性や自由』を対立概念と捉えているのです。
芸術(能)、スポーツ、学問などの様々な分野において、型を学ばない独学だけでは、すぐに成長が止まってしまいます。逆に型を身につけると、却って自分の世界、つまり個性が広がってくる。そして自分が努力して壁を打ち破った時に、本当の自由が広がるのです。
【Ⅴ】国語教育を通して 今後の人生で生きる力となる知識を伝え 情緒を育む
日本人で初めてノーベル物理学賞を受賞された湯川秀樹博士は、著書『創造的人間』の中で、「創造力は記憶力に比例する」、知識を頭に詰め込むことを単純に否定する考え方には警戒が必要であると述べています。「記憶というものは極めて重要であって、創造的な仕事は、相当量の系統だった知識の蓄積(記憶)があってこそ初めて可能なのです」
型と個性、型と自由。これらは対立しないのと同じく、「知識」と「創造」もまた対立概念ではないのです。真に創造的な仕事は知識の蓄積から生まれてくるように、国語教育は、その子供たちの今後の人生に有意義となる知識や情緒、美的感受性を伝えなくてはなりません。
【Ⅵ】国語は、全ての活動の基礎
私達は国語(日本語)を用いて生活している。聞く、話す、読む、書く、感じる、考える 等々。ここで大切なのは、情報伝達だけではなく、感じる・考えるなどの全ての知的活動は国語を用いてなされるのです。すなわち、全ての知的活動は、国語なくしては成り立たないのであって、私たちは自分の国語力に相応した思考しかできないのです。
【Ⅶ】国語力→語彙力→漢字力
国語力とは語彙力です。そして日本語の語彙の半分以上は漢字なので、国語力を身につけようと思えば、漢字力を身につけなければなりません。そしてそれら漢字力を身につけるには、脳に可塑性のある幼児期から小学校低(中)学年頃までが適しているのです。
一国の文化は その国の国語に帰着する
国語力とは語彙力であり 語彙力は漢字力が培う
脳に可塑性のある幼児期こそが 漢字吸収の最適期である
一国の文化は その国の国語に帰着する
国語力とは語彙力であり 語彙力は漢字力が培う
脳に可塑性のある幼児期こそが 漢字吸収の最適期である
教材の開発は、大人が自分の頭の中で易しい難しいを考えるのではなく、目の前の子供に当たってみなくてはなりません。実際に子供の発達段階を研究し、子供の実態に当たれば、読みに関しては、かなより漢字の方が易しいと感じていることはすぐに分かります。そこで、漢字は読み書き同時指導ではなく、読みを先行させることが子供の発達段階にあっていて、漢字力ひいては国語力を早く大幅に高めることができるのです。
【Ⅷ】国語力があれば美的感受性や情緒が養われる これらは教養と呼ばれるにふさわしく教養から大局観が養われる
これからの世界を考える時、経済力や軍事力以外に、日本の文化力というものが鍵になると思います。
先ほどから述べているように、一国の文化はその国の国語に帰着するという真理から、国語をどのように捉えるといいかということになります。国語教育は大きく二つに分けられ、●先ず第一は、【Ⅶ】ですでに述べたように、国語力→語彙力→漢字力 という国語力として基礎の部分です。
●第二は、その国の民族に特有の美的感受性や情緒の部分です。
なにかに触れた時に美しいと感動する美的感受性や、勇気、卑怯を憎む心、周りの人を気遣う心、清潔を好む心、惻隠の情 など多数あげられますが、私は日本人特有の美しい情緒として、『もののあはれ』を挙げたく思います。古来日本人は、散っていく桜の花や秋の虫の音色に自分の命の儚さを重ね合わせ、すべてのものは移り変わっていくのだという無常観を胸に宿してきた民族です。
それは平家物語など多くの著作や、また江戸時代に各地域を旅し歌い継いできた琵琶法師の存在からも明らかです。そしてそれらは、『もののあはれ』という言葉に行きつき、無常観を色濃く表しています。このように先人たちが紡いできた美的感受性を古典を通して知り、そこに命を重ねていくことこそ文化の伝承だと思います。
私達は実体験に加えて、古典や読書を通じて、この様な情緒を引き継いでいくのです。これこそ教養であり、教養は大局観をもたらします。人間の知恵の集積である古典・名文を学ぶことで、全体を俯瞰し、細部にこだわりすぎることのない大局観が養われます。
【Ⅸ】文明論
アメリカの国際政治学者サミュエル・ハンチントンをはじめ、現在多くの人により文明論が展開されています。世界の文明を八つ前後に分類している中で、例えば中華文明とか西洋文明とか、いずれも地域や宗教が名に冠されていて、一つの文明の中に複数の国が分類されています。その中で、日本だけが唯一、どの文明論においても日本文明と位置づけられ、日本文明には日本一国が属している。つまり、“一国一文明”の独自の国だと。
その理由は、日本の先人たちが、漢字かな交じり文を発明したことが契機となり、日本独特の文化の発展を見せた。すなわち、日本に入ってきた漢字から独自の万葉仮名を作り、奈良時代後期から平安初期には、仏典を読み学ぶ際に早く記述したいという欲求からカタカナを生み出し、外国語を日本語の話し言葉の順、すなわち漢字かな交じり文にして読み直すという途方もない試みを成し遂げました。これら日本語の成り立ちの結果、ここにできた日本語の構造や社会事情から、平安時代には女性による著作もなされました。
『古事記』『日本書紀』をはじめ、奈良・平安時代から江戸時代にかけて日本一国が生んだ文学は、同期間に全ヨーロッパの生んだ文学を凌ぐそうです。数学なども含め多様なジャンルにおいて、質・量ともに、日本一国でヨーロッパの全ての国の著作を合わせたものを凌駕していると言われています。これは驚くべきことです。
哲学や数学、物理などの学問を母国語で表せる日本語は、世界でも有数の言語です。日本の発展は、日本語に負っている。これらを生み出した先人には感謝してもしすぎることはありません。
【Ⅹ】本屋がなくなれば日本は滅びる
●イギリスの元ブレア首相は「七歳の児童たちの読書量が、将来の世界における英国の位置そのものである」と言いました。国民の読書量と国力は一対である。
●数学者の藤原正彦氏は「江戸末期、江戸に来たイギリス人達は、普通の庶民が本を立ち読み(それだけの本屋があったことにも驚きです)している姿を見て『この国は植民地にできない』と早々と諦めました。江戸時代中期から末にかけての識字率は、日本では70~80%、同時代の英・仏では20~30%と言われています。『自国を統治できない無能な民のためには我々が代わって統治してあげる』というのが植民地主義の論理でしたが、庶民が立ち読みする光景は本国にもないもので日本の文化力に驚いたのです。」続けて「読書は国防となるのです。書店数の激減は将来の暗雲と言えます」と記され、後ほど『本屋を守れ』という本を出版されました。…致知6月号より一部引用(安井一部改変)
【Ⅷ】において、今後の世界では軍事や経済力以外にその国の文化が鍵になると記しましたが、すでに150年昔から、これらのことが考えられていたのです。
【Ⅺ】最後に
本来なら、3話ぐらいに分けて執筆する内容(一般の文化論と安松幼稚園の国語教育)を今回まとめて記述してしまいましたので、読みづらい稿となってしまいました。頭の中で整理しながら根気よくお読みいただくことを期待しております。
結論:私たち大人も子供も、もっと本を読みましょう!!
個人が情緒豊かになれるかという問題とともに、日本国の存亡にもかかわりますぞ!!
付録:続けて、情緒 美的感受性に関するお母さんからのお便りをお読み下さい。
安松幼稚園の国語教育において、日本に伝わる文化や歌唱などを通じて、児たちに、日本人としての情緒や美的感受性が育まれていく過程を、お母さんからの2通のお手紙で紹介します。
☀一つめは俳句指導に関してのお手紙です。
●幼稚園児にここまで情緒が育つものかと
―― 子供が大人より五感で春を感じ
うぐいすを見て 俳句を詠む姿は まるで長老のようで
本当に幼稚園児かと思うぐらいでした ――
年中 保護者
過日、子供が幼稚園のバス停に行く途中の公園で、ふと立ち止まり遠くの木を見上げていたので、どうしたのか聞くと、「きれ~い! 白いお花が咲いたね。昨日は咲いてなかったのに。暖かくなってきたからお花が咲いたんだね」と。
私はいつも急ぎ足で、全く目にも留まっていなかった木に、白い木蓮の花がたくさん咲いていました。そして少し歩き始めると、近くの木にうぐいすが三羽止まり、私が「あ、うぐいす」と言うと、息子が大きな声で
「うぐいすや ちょいと来るにも 親子連れ」と俳句を詠んで、
「ママ、春が来たね~。気持ち良いね~。」と言って、軽やかな足取りでバス停に向かいました。
朝の小さな一コマなのですが、子供が大人より五感で春を感じ、うぐいすを見て俳句を詠む姿は、まるで長老のようで、本当に幼稚園児かと思うぐらいでした。(笑)
まだ5歳少しの子供が、これだけの感性と表現が身に付いて育ってくれている事を嬉しく、俳句を幼稚園で取り入れてくれる事は、知識として学ぶという事だけではなく、感性・情緒をも磨き育ててくれているんだなと。
家ではなかなか学べない事を教えて下さる安松幼稚園、その先生方の熱心なご指導に、改めて感謝しました。
この内容は、雑誌『致知』の2025年6月号にも 取り上げられています。
☀ 二つ目は、歌唱指導についてのお手紙です。
先生方の熱意ある指導から引き出された
子供の溢れんばかりの情緒・感性に涙
年中保護者
先日の音楽会、本当に一生懸命に先生の指揮を見て追って、真剣に歌う子供達の姿に涙が溢れ、先生方の熱意ある指揮にも感動しました。心より感謝申し上げます。
今までは、家で歌ったりすることは少なかった息子ですが、音楽会が終わった今も毎日よく歌っています。
その中の出来事なのですが、主人とともに涙したことがありました。
息子はよく「年長さんの声はすごくきれいやねん」と言っています。
特に『やさしさに包まれたなら』が好きなようなので、CDを聞かせてみました。
すると息子は、「これ、違う……」と言いました。(以下、私達の会話です)
<母>
「何が違うの?」
<子>
「声も違うけど……年長さんが歌ってるやつ聞く方がいい」
<母>
「どうして?」
<子>
「年長さんの、きれいやねん。とくにな、あの『カーテンを開いて……目に映るすべてのことはメッセージ』が好きや。あれ聞くと、涙出てくるん。
なんかなぁ、勝手にぶわーって出てくるん」<母>
「どんな気持ちなの?」
<子>
「……きもちよくて……あったかくてなぁ……やさしい気持ち。
いつも練習で聞いてて、幼稚園で泣いてしまったん、恥ずかしいからかくしたけどな」
と、ニッコリ笑いました。
息子の言葉に夫婦で驚き、涙がこぼれました。
まだ“感動”という言葉を知らないのでこのような表現になっていますが、息子の気持ちは十分に伝わりました。息子も、大人と同じように、歌を聴いて感動する心が育っていたのですね。
もうなんだか……息子の成長に夫婦で涙です。
年中に転入しわずか3ヶ月、>先生方の日々の熱意と誠意ある指導のおかげで、歌うということだけでなく、このような素晴らしい情緒・感性を育んで頂いたこと、本当に嬉しく心から感謝申し上げます。